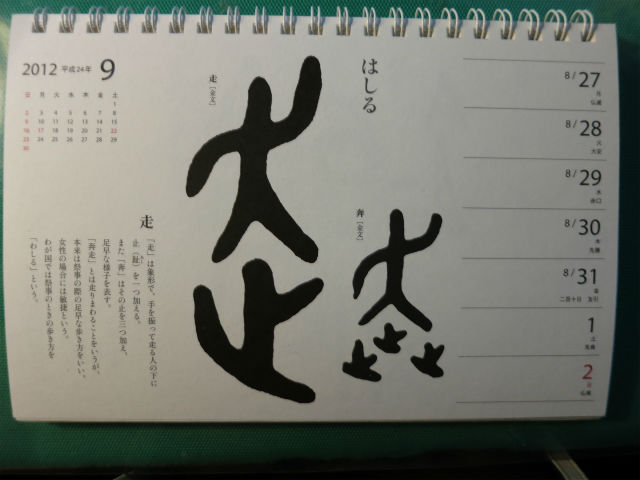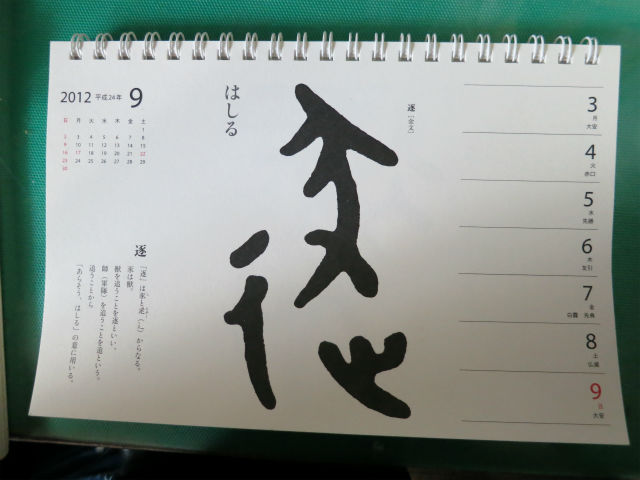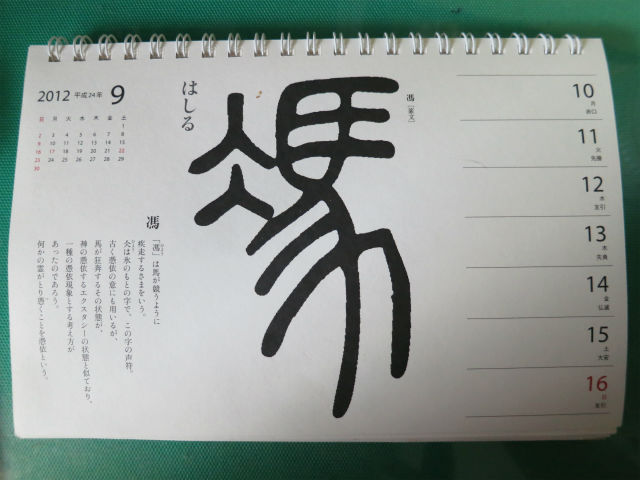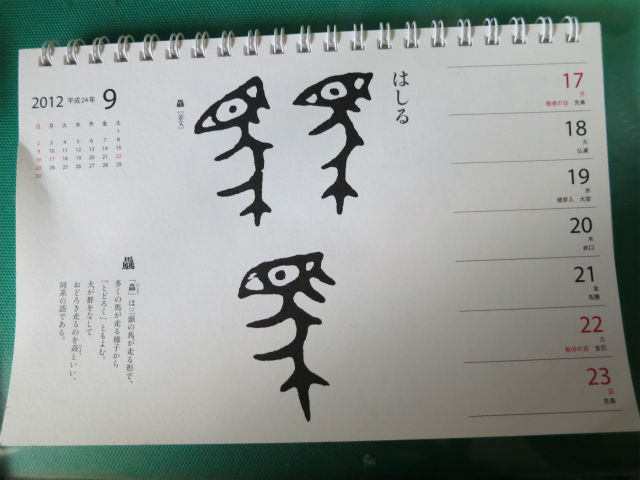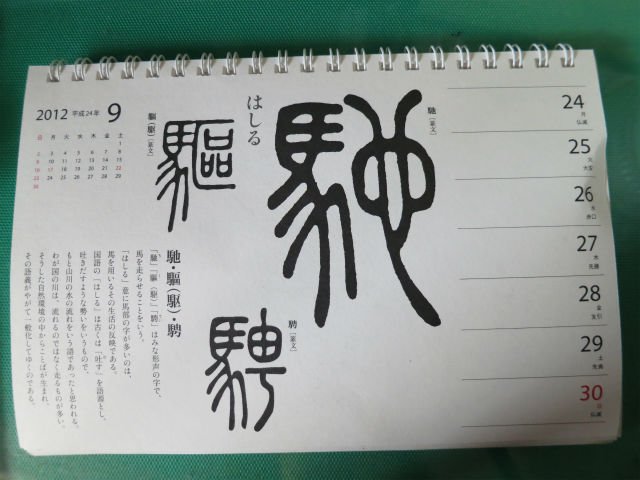漢字暦
走
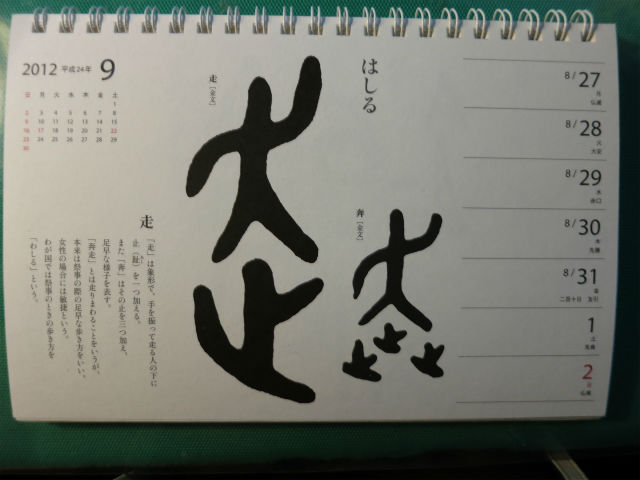
==以下引用===========
「走」は象形で、手を振って走る人の下に止(趾あし)を一つ加える。
また、「奔」はその止を三つ加え、足早な様子を表す。
「奔走」とは走りまわる人のことをいうが、本来は祭事の際の足早やな歩き方をいい、女性の場合には敏捷という。
わが国では祭事の時の歩き方を「わしる」という。
更新日2012年8月27日(月)
ここで「はしる」という訓のある字は、
「走」に始まり、「逐」「憑」「驫」「馳・驅・騁」の7字が挙げられている。
甲骨文では耳の形が大きく、口に手を当てている形。
※逐(を遂と間違えて記載しいました(~_~;)、駆逐のチク、と遂行のスイですね。
逐
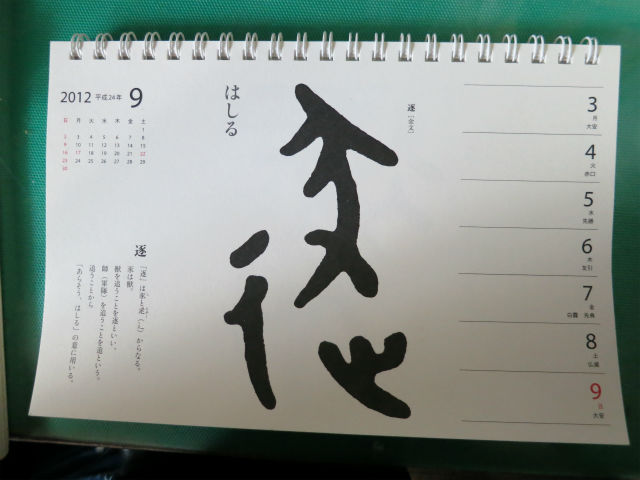
==以下引用===========
「逐」
は豕(し)と辵(ちゃく)(しん)(辶 テンは一つ)からなる。
豕は獣。
獣を追うことを逐といい、師(軍隊)を追うことを追という。追うことから「あらそう、はしる」の意に用いる。
これは驚きました。
師とは、「人を教え導くもの」だと思っていましたら、
「軍隊」
という意味であるとは。

角川大字源をみると、
師: 形声、意符の■(たい 師の左の部分 臀部の盛り上がった形から小丘の意に借用された)→古代、堆丘に軍隊が止駐していたので、軍隊の意に用いる。
音符の帀(シ 丘の意)からなる。軍隊が駐屯する小高い丘の意・のち軍隊の意の専用字となり、借りて「おさ」の意に用いる。
憑
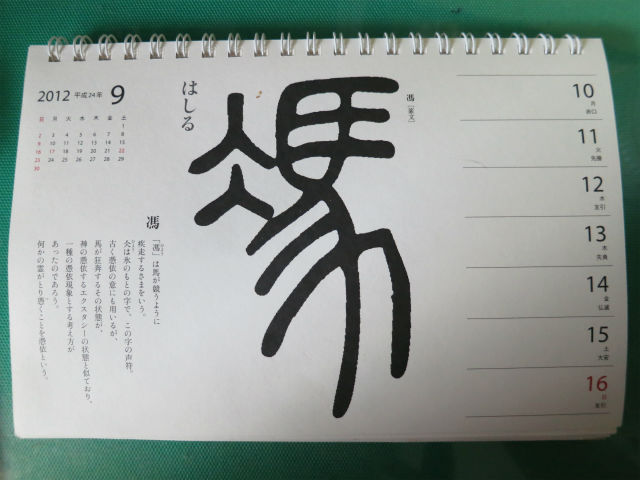
==以下引用===========
「憑(ひょう)}は馬が競うように疾走する様をいう。

(ひょう)は氷のもとの字で、この字の声符・
古く憑依の意にも用いるが、馬が狂奔するその状態が、神が憑依するエクスタシーの状態と似ており、一種の憑依現象とする考え方があったのだろう。
何かの霊が取り付くことを憑依という。
更新日2012年9月14日(金)
驫
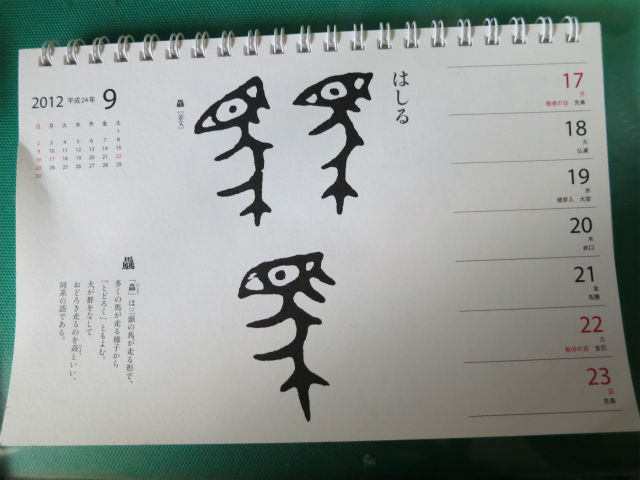
==以下引用===========
「驫(ひょう)」は三頭の馬が走る形で、多くの馬が走る様子から、「とどろく」ともよむ。
犬が群れをなしておどろき走るのを猋(ひょう)といい、同系の語である。
馳・驅・騁
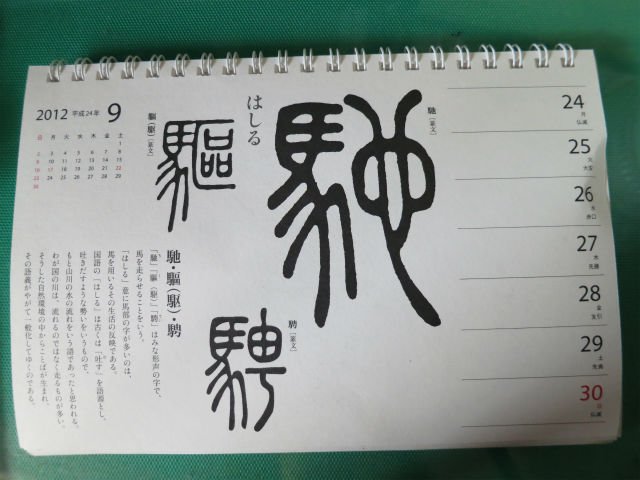
==以下引用===========
「馳(ち)」「驅(駆)(く)」「騁(てい)」はみな形声の字で、馬を走らせることをいう。
「はしる」意に馬部の字が多いのは馬を用いるその生活の反映である。
国語の「はしる」は古いくは「吐(は)す」を語源とし、吐き出すような勢いをいうもので、もと山川の水の流れをいう語であったと思われる。
わが国の川は、流れるのではなく走るものが多い。そうした自然環境の中から言葉が生まれ、その語義がやがて一般化してゆくのである。
更新日2012年9月14日(金)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 月
上に戻る