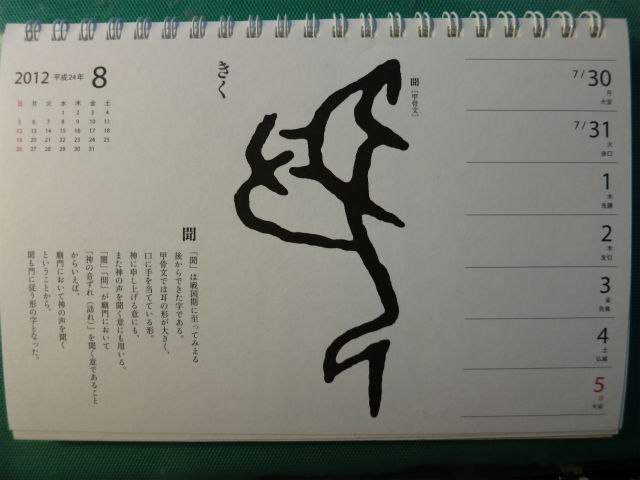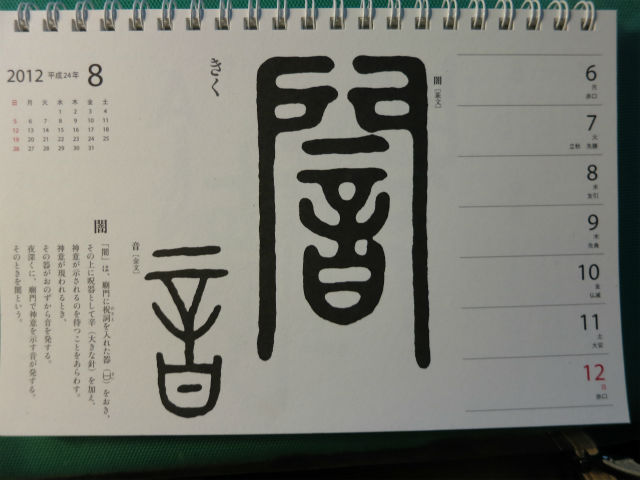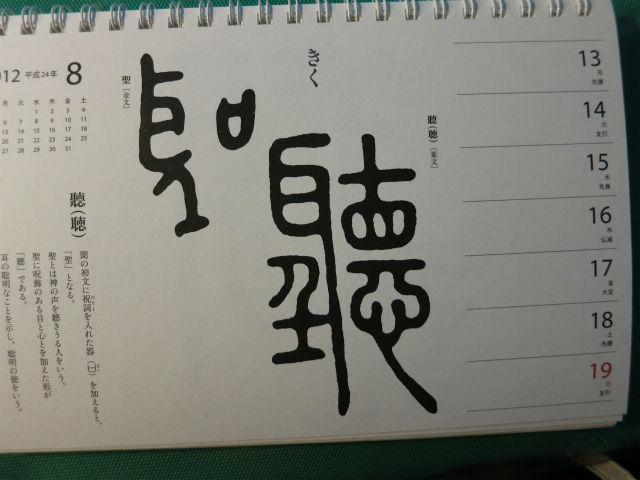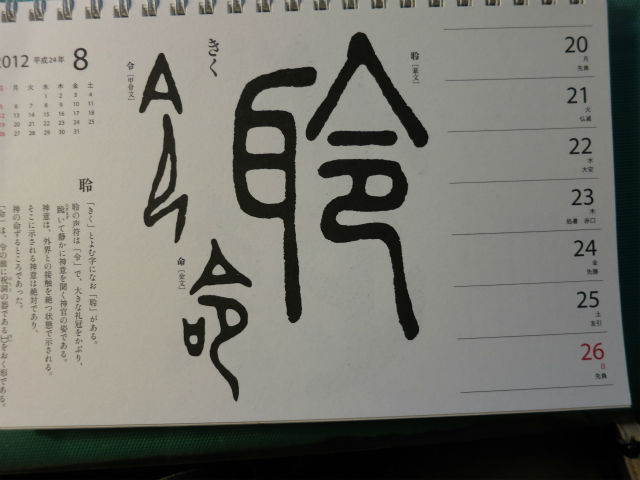漢字暦
聞
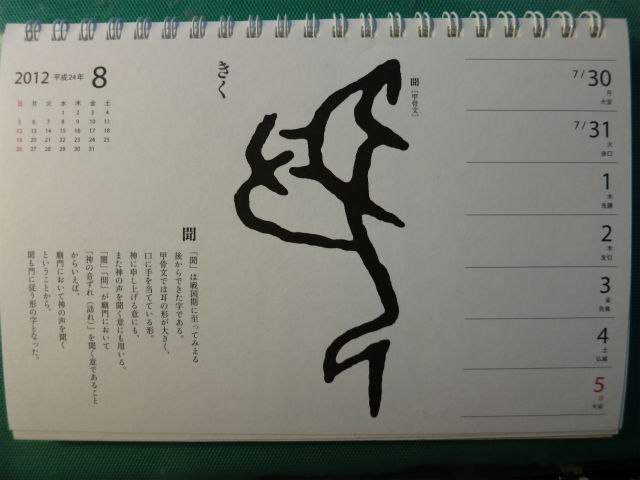
==以下引用===========
「聞」は戦国期に至ってみえる後からできた字である。
更新日2012年8月6日(月)
ここで「きく」という訓のある字は、
「聞」に始まり、「闇」「聴」「聆」の4字が挙げられている。
甲骨文では耳の形が大きく、口に手を当てている形。
神に申し上げる意にも、また神の声を聞く意にも用いる。
「闇」「問」が廟門において「神の音ずれ(訪れ)」を聞く意であることからいえば、
廟門において神の声を聞くということから、闇も門に従う形の字となった。
闇
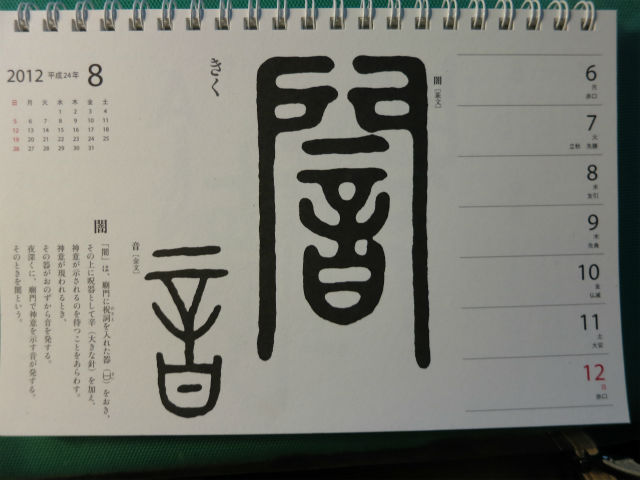
==以下引用===========
「闇」は廟門に祝詞を入れた器(

)を置き、その上に呪器として
辛抱(大きな針)を加え、神意が示されるのを待つことをあらわす。
神意があらわれるとき、その器がおのずから音を発する。
夜遅く、廟門で真意を示す音が発する。その時を闇という。
更新日2012年8月13日(月)
う~~ん(~_~;)左下の字ですね=音
聴
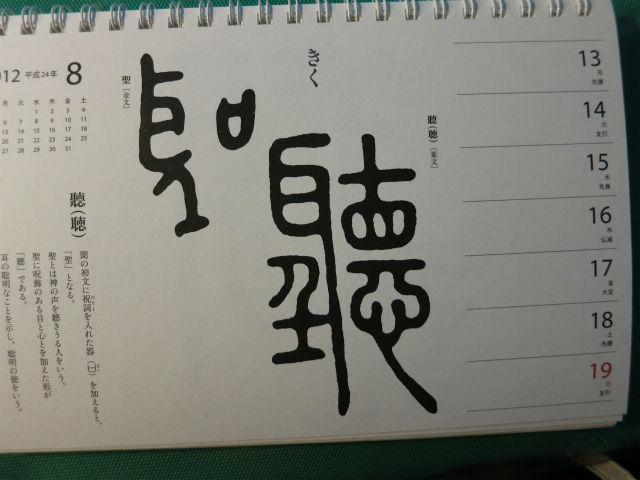
==以下引用===========
聞の処分に祝詞を入れた器(

)を加えると、「聖」となる。
聖とは神の声を聴きうる人をいう。
聖に呪飾のある目と心とを加えた形が「聴」である。耳の聡明いことを示し、聡明の徳をいう。
更新日2012年8月13日(月)
聆
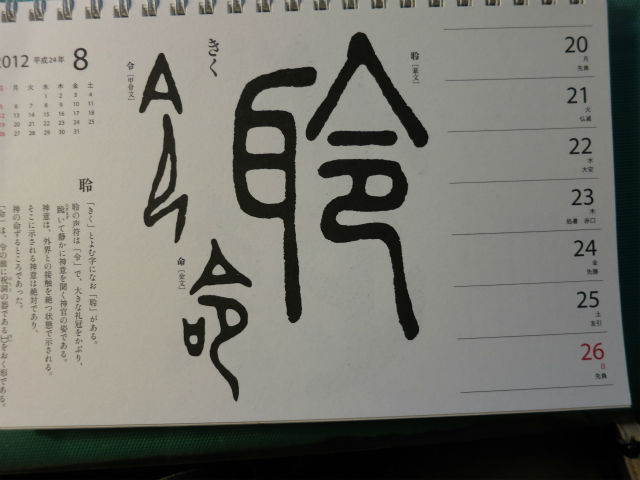
==以下引用===========
「聞く」とよむ字になお「聆」がある。
聆の声符は「令」で、大きな礼冠をかぶり、跪いて静かに神意を聴く神官の姿である。
神意は、外界との接触を絶つ状態で示される。
そこに示される神意は絶対であり、神の命ずるところであった。
「命」は令の前に祝詞の器である

をおく形である。
更新日2012年8月21日(火)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 月
上に戻る